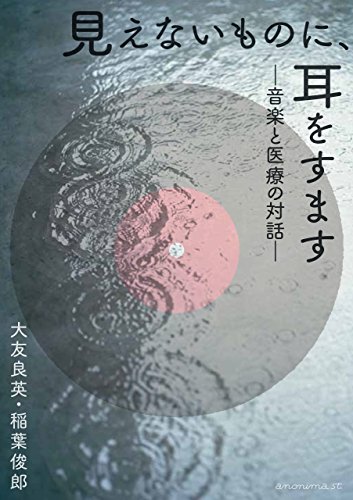医師の稲葉俊郎さんとの共著「見えないものに、耳をすます」のなかで、音楽家の大友良英さんが音楽とのかかわり方について興味深いことを言っていた。仲間はずれにしない音楽。これは音楽に限らず、居心地の良い空間、ひいては快適な暮らしをつくるうえで、大切な姿勢だと思う。
稲葉:大友さんがやっていることって、仲間はずれになる人を作らずに、誰にでも居場所を感じさせてくれる音楽というか。ちゃんと適切な居場所がみんなにあるんだとわかっていても、「あなたはこれだよ」って示すのは難しいと思うんです。でも大友さんの音楽にはそれを感じるんですよ。
大友:うれしいなあ、そんなこと言われると。たとえば学生のバンドで、ドラム、ギター、ベース、管楽器ってあって、管楽器は何人いてもいいんだけど、ベースやドラムってひとりだけですよね。そうすると一年生とか補欠の人は、脇に座っていたりする。そういうのを見るのが、僕はすごく辛いんです。音楽なんだから一緒にやったらいいのにって思う。それは別にその子がいじめられているわけじゃないんだけど、音楽の中で、ヒエラルキーができてしまうのがイヤなんです。(中略)たとえば、トランペットで「プッ」と音が鳴らなくて「フーッ」と鳴っちゃう人がいたとしたら、「フーッ」という音でもちゃんと取り込むような音楽を作ればいいんです。そんな感じで、やっている人たちの間にヒエラルキーができてしまわないように音楽を作りたいなって思っています。
私は大学時代、クラシックギターのアンサンブルサークルに所属していた。ひとつの曲を大まかに3つのパートに分けて、重奏するという形だった。主に主旋律を弾く1stパートが当然目立つのだけれど、バックでリズムを刻んだりベースラインを弾いたりする2ndパートや3rdパート(曲によっては4thパートをつくるなどバリエーションがあったような気がするけれど、よく覚えていない)がなければただ主旋律が流れているだけで、曲として成立しない。3つのパートが合体してドーンと大きな音楽が生まれたと感じる瞬間の高揚感は、音楽を演奏する者でないと味わえない特権的な快感だった。
大学生が半ば趣味のような気持で取り組んでいて、楽器の習熟度や練習量、そもそものサークルに対する熱量に個人差がある以上、どうしても本番までにきちんと演奏できない部員が現れたりする。それ以前に、バイトが忙しくてそっちに専念したいからと本番の前に辞めてしまったりする人もいたと思う。そういう部員によって演奏の出来具合に差がある集団において、曲がりなりにも部長という立場だった自分は、もっと「仲間はずれ」をつくらない工夫ができたのではないか。そのことに、大学を卒業して16年経ったいま、ようやく気づいた。上手に演奏することはもちろん大事。練習に来ない不真面目なヤツに注意して来てもらうようにすることも大事。しかし、そうでなくても演奏会は部員皆で楽しめるものだということ(それが音楽というものでしょう、ということ)を、部長が率先して部員に示すべきだったのではないか。たとえばどうしても弾けない部員や、恥ずかしくて音が小さい部員がいたりするのであれば、そういう部員でも堂々と演奏できるように個別にパートを作ったらいい。全体を3パートに分けて全ての部員をそのどれかに充てなければいけないというルールなんて、ない。それくらい自由にやっている気ままなサークルだったのだから。
翻ってそのことは、いまの私の自営業でも言えるのかもしれない。本を売る私は今、「自分自身が読んで良かったと思える本」「お気に入りの本」「オススメの本」ばかりを仕入れて紹介している。何も愛着のないものを紹介するより余程良いことだとは思っているけれど、それだけではどうしても自分というフィルターを通した本しか紹介できず、偏ってしまう。私の想いに共感してくれる方にはぴったりの選書かもしれないけれど、価値観がまるで違う方にとっては、何も面白くない選書に見えるだろう。それは、「『私の好きなテイストの本』をわかってくれない人は来なくて結構」という姿勢に他ならない。本に興味があって自分が発信するものに近寄ってくれる方々をひとつの集まりとすると、その集まりからはじき出してしまう、つまり仲間はずれにすることにつながる。その「仲間はずれにされた人」を見るのが辛いのは、大友さんにしても、私にしても、同じだ。
仲間はずれにしない。胸に刻んで大事にしたい言葉だ。